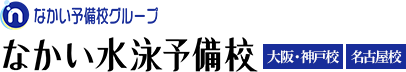臨床発達心理士の子どもの発達コラム 〜子どもを観察してみよう〜
臨床発達心理士の趙です。
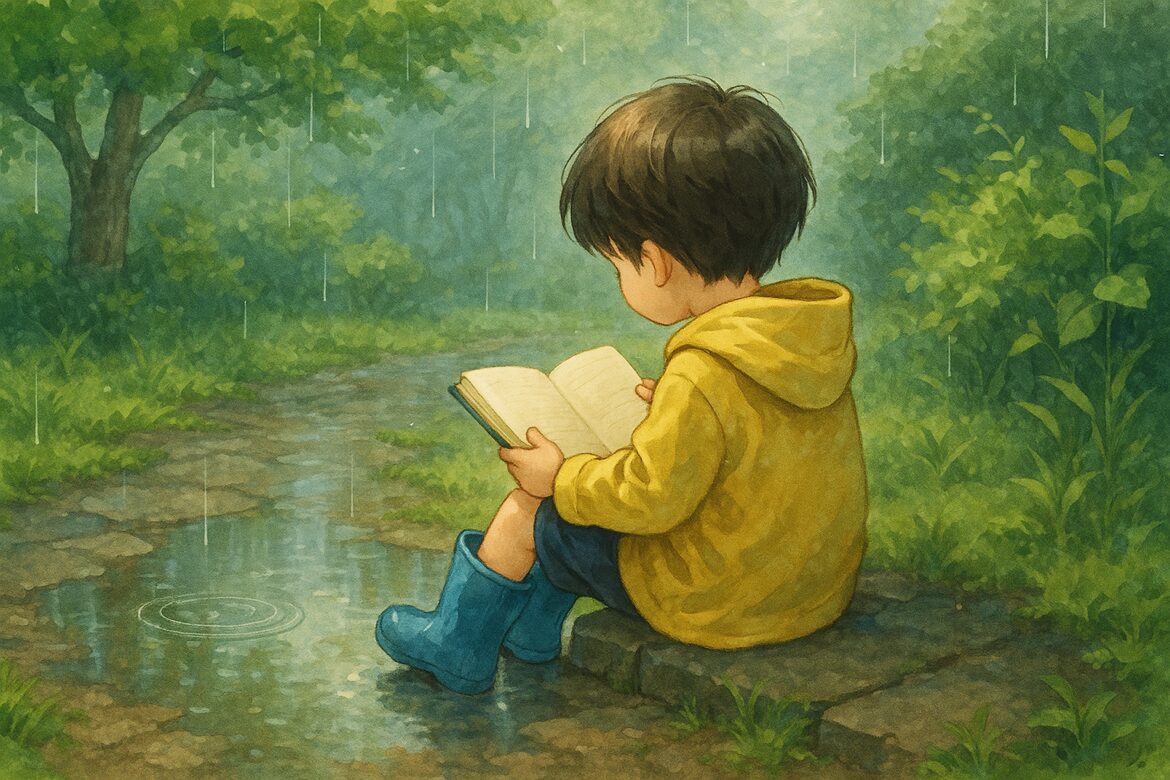
6月になると雨の天気が増えて、湿度が上がっていますね。
大人でも体が重く感じたりして、なかなか厳しい季節だなと思います。
ダルーとなっている子どもたちも多いのではないでしょうか。
しかし、4gたうからの新しい環境にては、2ヶ月経ってようやく慣れてきている状況でもあります。
少し環境に対しては、落ち着いてきているかもしれませんね。
6月になると、子どもたちが少しのびのびと過ごせるようになってきますので、今日はそんなお話をしたいと思います。
<環境への適応>
4月からの2か月間は、子どもたちなりに“がんばって適応する”時期でした。
・忘れ物しないように気を張る
・友達に合わせようとがんばる
・先生の言うことをちゃんと聞こうと頑張る
などなど、頑張ったことも多かったのではないでしょうか。
その結果、5月に入って“ちょっとしんどい”が顔を出す子もいました。
でも6月、少しずつ“自分のペース”を取り戻し始めているのではないでしょうか。
ここで見えてくるのが、その子の“素の姿”。
たとえば、
- 集団行動にちょっと疲れて、休み時間は1人で本を読むようになる
- 算数の授業ではつまずかないけど、音読のときに急に声が小さくなる
- 友達との関係に悩むよりも、1人遊びの方が楽しいと感じる
こうした「行動の変化」は、心の余裕が生まれたからこそ表れるものだと言えます。
■今こそ、見えてきた“気になるところ”を拾うとき
6月は、実は保育や教育の現場でも「気になる行動がはっきりしてくる」と言われる時期だと言われます。
4月・5月は“適応する”ことを頑張っていたので、見えづらくなっていたのかもしれません。
「気になる行動」が見られたときには、このタイミングで、大人が「なぜそうなるのか?」を一緒に考えることが、今後の支援のヒントになります。
■観察は理解の第一歩
6月は、少し立ち止まって、子どもの行動を観察すると良いでしょう。
子どもの色んな行動には、必ず背景があります。
ぜひ観察をしながら、子どもの行動について考えていけると良いですね。
■さいごに ―「今」の観察は、未来へのギフト
6月に見えてくる“気になる行動”は、実は“これから”を考えるうえでとても大切な材料です。
立ち止まって、「この子は今、どんな状態なんだろう?」と想像してみるところから始めましょう。
子どもの発達は、決して一直線ではありません。
“ちょっと落ち着いた今”を、大人にとっても「観察と理解の時間」にしてみませんか。
~なかい水泳予備校では、現在スイミングの個別指導を行う講師を募集しています~
「水泳が好き」「子どもと関わる仕事がしたい」「指導経験を活かしたい」
そんな想いのある方をお待ちしています!
ご興味のある方は、お気軽に採用ページをご覧ください。
https://nakaiyobikou-saiyou.jp/