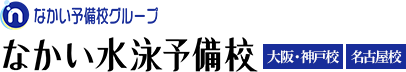臨床発達心理士の子どもの発達コラム ~季節の変わり目と子どもの心と体~
9月は、夏から秋へと移り変わる季節です。朝夕は涼しくなってきたかと思えば、昼間はまだ真夏のような暑さが残る。さらに台風シーズンも重なり、気圧の変化も激しい。この「揺れ」が、子どもたちの心と体にも大きな影響を与えます。
大人であっても「なんとなく体が重い」「気分が落ち込みやすい」と感じることがあるように、子どももまた季節の変わり目に敏感です。ただし子どもは自分の不調を言葉で的確に表現することが難しいため、親や先生に「しんどい」と伝えられず、行動や態度に出やすくなります。
季節の変化がもたらす体調への影響
まず、気温差。朝は肌寒く、昼間は汗ばむ。この温度差に体がついていけず、疲れやすさや風邪をひきやすさにつながります。自律神経のバランスが崩れると、食欲が落ちたり、頭痛や腹痛を訴える子も増えてきます。特に敏感な子は「なんとなく体がだるい」という状態が続き、勉強や運動に集中できなくなることもあります。
次に、台風や天候の不安定さ。低気圧の影響を受けると体が重く感じられたり、頭痛が出たりすることがあります。子ども自身は「気圧のせい」とは分からず、戸惑うことも少なくありません。
季節の変化が心に与える影響
体の不調と同じくらい、心の揺れも目立ちやすいのが9月です。夏休み明けの学校生活に慣れようと頑張っている時期と、季節の変わり目がちょうど重なります。
「朝起きるのがつらい」「学校に行きたくない」といった行動の背景には、単なる怠け心ではなく、体調や気分の不安定さが関わっていることが多いのです。
また、気候の変化による「なんとなくの不安」や「イライラ」は、敏感な子どもほど強く感じます。本人も理由が分からずに涙が出たり、ちょっとしたことで怒りっぽくなったりすることもあります。こうした反応を見て大人が「どうしてそんなに情緒不安定なの?」と叱ってしまうと、子どもはますます自分の感情に自信をなくしてしまいます。
親ができるサポートの工夫
季節の揺れを乗り越えるためには、生活リズムを整えることが基本です。
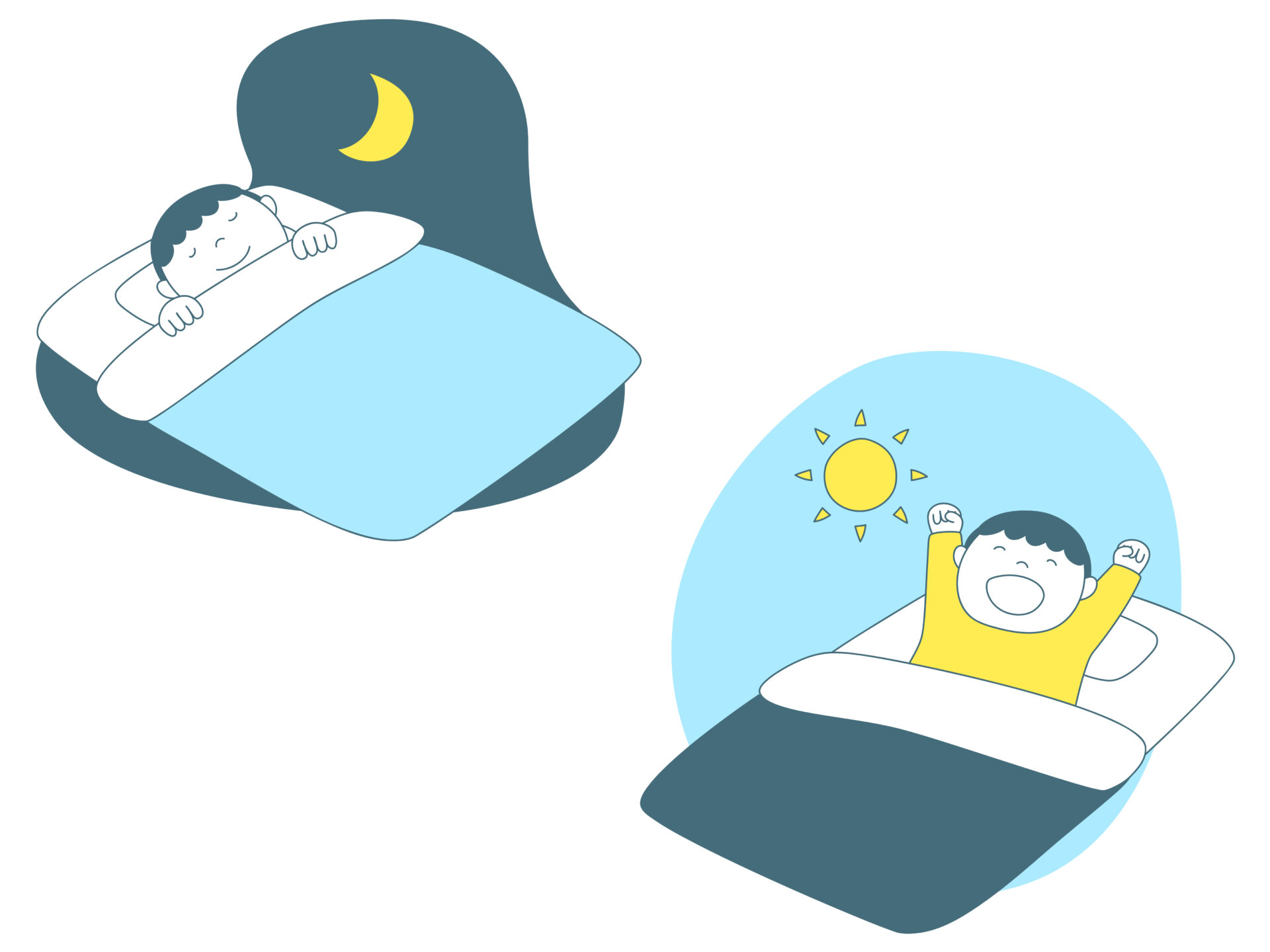
- 睡眠:夜更かしになりがちな夏の習慣をリセットし、早寝・早起きのリズムを意識する。
- 食事:冷たい飲み物やさっぱりした食事ばかりでなく、温かい汁物を取り入れて体を内側から温める。
- 運動:涼しくなる夕方に軽い散歩や遊びを取り入れることで、気分転換にもつながる。
さらに、心理面のサポートとして大切なのは「揺れるのは自然なこと」と伝えることです。
「この時期は大人でもしんどくなるんだよ」
「イライラするのは体ががんばって季節に合わせてる証拠なんだね」
といった言葉は、子どもにとって安心材料になります。
また、行動に出ている小さな変化に気づき、受け止めてあげることも大切です。たとえば「最近、朝が少しつらそうだね」「なんだか元気ないみたいだね」と声をかけることで、子どもは「分かってもらえている」と感じ、安心できます。
まとめ ― 揺れる時期だからこそ、育つ力がある
9月は、心も体も不安定になりやすい季節です。けれど、この「揺れ」を経験することで、自分なりに整える力を少しずつ育てていくことができます。
子どもたちは、完璧に元気でいる必要はありません。気温や気圧の変化に揺れながらも、「眠るとちょっと楽になる」「温かいご飯を食べると落ち着く」「話を聞いてもらうと安心する」といった、自分を整える方法を見つけていくのです。
大人にできるのは、その小さな発見を一緒に喜び、見守ること。揺れる季節を乗り越えた先には、またひとつ成長した子どもの姿が待っています。