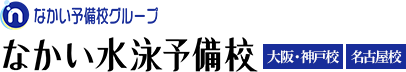臨床発達心理士の子どもの発達コラム 〜運動の秋!〜
体を動かすことは、“心”を動かすこと ― 発達支援としての運動の力
こんにちは!臨床発達心理士の趙です!
ようやく涼しくなってきましたね!
子どもたちも運動会や体育の授業、外遊びなどで体を動かす機会が増えてきました。
“体を動かすこと”には、単に運動能力を高める以上の意味があります。
それは、“心を動かす”ということ。運動は、子どもの心や発達に深く関わっているのです。
■ 動くことで「できた!」を感じる
運動には、「自分の体を思い通りに動かす」という感覚的な喜びがあります。
跳ぶ・走る・投げる・バランスを取る。これらはどれも、自分の体をコントロールしながら目的を達成する活動です。
「うまくできた!」「さっきより速く走れた!」という達成体験は、子どもの心の中に小さな自信の種をまきます。
この「できた!」という実感は、学習意欲や対人関係にも広がっていきます。
なぜなら、子どもは「成功体験」を通して、自分の努力が成果につながることを学ぶからです。
それが「やってみよう」「もう一回!」という気持ちを生み、挑戦する心を育てていきます。
■ 運動が「情緒」を整える
体を動かすことは、心の安定にも深く関わっています。
緊張したり不安を感じたりする時、体がこわばることがありますよね。
逆に、ゆったりと体を動かすことで、呼吸が整い、気持ちも落ち着いてくる。
これは、身体と心がつながっていることの表れです。
特に、感情のコントロールが難しい子どもや、切り替えが苦手な子どもにとって、
“体を使って発散する”ことはとても大切です。
ボールを蹴る、鬼ごっこで走る、縄跳びを続ける。
こうした動きの中で、エネルギーを「行動」に変換することができます。
さらに最近の研究では、運動が脳の神経伝達物質の働きを促し、
集中力や注意の持続にも良い影響を与えることがわかっています。
つまり、運動は心身のバランスを整える“自然なメンタルケア”でもあるのです。
■ 脳と身体は、発達のなかで常に手を取り合う
「脳と身体は別々のもの」と思われがちですが、実際には密接に結びついています。
たとえば、バランスを取る・タイミングを合わせるといった動きは、
脳の中で「空間認知」「注意」「実行機能」といった領域と連動しています。
運動を通して体を調整する経験は、思考や学習の基盤にもつながっているのです。
発達に凸凹のある子どもたちの中には、体の使い方がうまくいかないために、
書く・読む・座るといった日常の学習動作にも困難を感じることがあります。
そんな時こそ、「運動あそび」を通して“からだの地図”を育てていくことが役立ちます。
たとえば、リズムに合わせて動く、模倣してポーズを取る、
バランスボールで弾む、平均台を渡る。
これらの遊びは、運動能力を鍛えるだけでなく、
身体感覚と脳のネットワークをつなぐトレーニングでもあります。
■ 「楽しい」が、すべての原動力
発達支援の現場でもよく感じるのは、子どもは「楽しい」と感じた瞬間に、
ぐんと集中力や持続力を発揮するということです。
逆に、「やらされている」と感じると、体も心もすぐに硬くなります。

運動が苦手な子には、できないことより“できること”を見つける視点が大切です。
ボールを受けるのが難しければ、転がすところから始める。
走るのが苦手なら、音楽に合わせて体を揺らすだけでもOK。
「できた」「楽しかった」の積み重ねが、少しずつ自信を取り戻すきっかけになります。
■ 心と体の育ちを、あたたかく見守って
まっすぐに走るのが得意な子もいれば、リズムに合わせて体を揺らすのが好きな子もいる。
一人ひとりの「好き」や「得意」を尊重しながら、
運動を“できる・できない”で評価するのではなく、“心が動いた瞬間”を大切に見つめたいですね。
体を動かすことは、心を動かすこと。
体育の秋に、そんなつながりを改めて感じる時間を持てたら素敵だと思います。