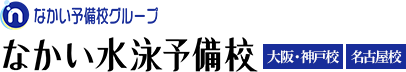臨床発達心理士の子どもの発達コラム 〜夏休みにできること〜
こんにちは!臨床発達心理士の趙です!
いよいよ夏本番。
子どもたちも夏休みになりましたね。
夏休みは、時間のゆとりがある分いろんなチャレンジができる期間でもあります。
今日はそんな話を書いてみます。
「夏休み、うれしい!」の裏側にあるもの
7月後半、子どもたちは「あと〇日で夏休み!」と目を輝かせます。
けれど、実はその先にあるのは、「自由」と「退屈」が紙一重の、不思議な時間ではないでしょうか。
いつもの時間割も、給食も、きまりごともない日々。
大人の目からは「のんびりできていいなぁ」と映るかもしれませんが、子どもにとっては「どう過ごしていいかわからない」「誰にも会えなくてさみしい」時間になることもあるのです。
自分で「つくる時間」が始まる
学校がない夏休みは、“与えられた時間”から“自分でつくる時間”への転換点。
毎日のスケジュール、遊び、学び、人との関わりも、ある程度自分で「選ぶ」ことができます。
この“選択”こそが、子どもにとって大きな成長のチャンスだったりします。
- 「今日は何をしよう?」と考える思考力
- 自分の“やりたい”を探す自己決定力
- 退屈に耐える忍耐力
- 一人で過ごす力や、誰かと交渉する力
「自由な時間」は、こうした様々な力を伸ばすための土壌になります。
「退屈」は悪いことじゃない
「ヒマ〜」「つまんな〜い」と言う子どもを見ると、大人はつい、「じゃあこれやってみたら?」「ゲームしていいよ」と、何か与えたくなります。
でも、“退屈”という時間こそが、子どもが「何かを生み出す」きっかけになることもあります。
ダンボールで秘密基地をつくってみたり、いつもより長い物語を思いついたり、ふとお手伝いに手を伸ばしてみたり。
退屈から試行錯誤して、自分の体験と世界をつくっていく。
そんなプロセスも、子どもの発達においては重要なポイントになります。
一方で、夏休みが“苦手”な子どもたちもいます。
- 規則正しく過ごすのが苦手で、生活リズムが乱れる
- 一人の時間が多くなり、不安や孤独感が増す
- 宿題や自由研究のプレッシャーが強くなる
- 家の中での関係(きょうだいや親子)が密になり、ストレスが増える
特に、「見通しのなさ」や「自由度の高さ」が苦手なお子様は、不安につながることもあるかもしれません。
保護者にできる “ゆるやかな支え”
子どもにとって、安心して過ごせる夏休みをつくるためにはどうすれば良いでしょうか。
保護者ができることは、「余白のある予定」と、「見守る距離感」のバランスかもしれません。
- ざっくりスケジュールを一緒に描く(例:午前は自由/午後は図書館、など)
- 「宿題、どこまで進んでる?」ではなく、「なんか面白そうなとこあった?」と問いかける
- 一緒に“退屈”を楽しむ(例:庭に出て空を眺める、氷を観察する、など)
- イライラしても「まあ夏やしね」と、温度を少し下げて付き合う
「やるべきこと」をこなす夏ではなく、「なんとなく豊かだったな」と子どもが感じる夏にしていけたら、それが一番の収穫です。
せっかくの夏休みです。子どもたちにも色んなチャレンジをしてほしいなと思います。