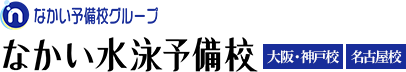臨床発達心理士の子どもの発達コラム 〜友達作り〜
臨床発達心理士の趙です。
4月になりましたね。
新しいクラス、新しい先生、新しい生活。
保護者の方にとっても、「うちの子、ちゃんとやっていけるかな…」と心配が募る時期です。
その中でも特に多いのが、子どもに「友だちはできたかな?」という不安。
実際、入学・進級の時期に「お友だちできた?」と子どもに聞くことはよくあるやりとりでしょう。
でも、ちょっと立ち止まって考えてみたいのです。
友だちって、絶対に必要なものでしょうか?
今日は、そんな友達作りの話をしたいと思います。
<「友だちがいない=問題」ではない>
「友だちがいない」と聞くと、つい心配になってしまうのは当然です。
私たち大人自身が「友だちがいることは良いこと」「いないのは寂しいこと」と捉えているからこそ、
子どもにも「誰かとつながっていてほしい」と願ってしまいます。
でも、発達段階や個性によっては「一人が落ち着く」子もたくさんいます。
実際に、遊びの時間は一人で絵を描いていることが多くても、本人は満足しているケースもあります。
むしろ、無理に誰かと関わることのほうが、ストレスになる子どももいるのです。
また、友だちを作ることに時間がかかる子もいます。
最初から誰かとワイワイできる子もいれば、環境に慣れてからじわじわと関係を深めていく子もいます。
ペースは子どもそれぞれです。
<親の「不安」は伝わる>
とはいえ、保護者の立場としては、やっぱり気になるのが当然です。
でもその「気になる」が、「今日は誰と遊んだの?」「仲良くしてる子はいるの?」「なんで一人でいるの?」と毎日のように子どもに聞いてしまうと、
子どもはこう感じるかもしれません。
「友だちがいない私はダメなのかな」
「親は友だちのことばかり気にしてるな」
「ちゃんと答えなきゃ、安心してもらえない」
こうなってしまうと、本来の「子ども自身の人間関係」ではなく、「親にどう答えるか」が優先されてしまうようになるかもしれません。
子どもは親の表情や口調から、びっくりするほど多くのことを感じ取っています。
だからこそ、親が「この子なりに過ごしてるなら、それでOK」と安心して構えることが、子どもにも伝わります。
<「見守る」って、実はむずかしい>
「見守る」と言うと簡単ですが、ここが一番難しいですね。
勘違いされやすいですが、“干渉しない”ことと“関心を持たない”ことは違います。
見守るとは、子どもの気持ちや行動に寄り添いながら、必要なときにそっと支えることだと思います。
友だちとの関係に悩んでいる様子があった時には、「困ってる?」と聞いてあげてほしいなと思います。
ただ必要以上に「友だちを作らせよう」としないことも、大事なサポートの一つなのです。
<友だちを作りたい子にはどうしたらいい?>
一方で、「友だちがほしいけどうまくいかない」と悩む子もいます。
そんなときには、以下のような方法が役立ちます。
- 「きっかけづくり」を一緒に考える
たとえば、「同じ本が好きな子を見つけたら話しかけてみる」とか、「おもちゃを貸してみる」といった行動のパターンを事前に練習しておくと、
ハードルが下がります。
- 「ひとりでも大丈夫」を土台にする
友だちがいない時間を否定せず、**「一人でも楽しいことがある」**という感覚があれば、人との関係もうまく築きやすくなります。
- 「友だちってどんな存在?」を話してみる
「友だちって、無理して仲良くするもの?」と子どもに投げかけるだけでも、価値観が整理されます。
数よりも“自分が心地よくいられる人間関係”が大事だという視点を持つことが、その子の人生を助けてくれるはずです。
<子ども自身の選択を、大人が支える>
友だちを作るかどうか、どんな関係を築くかは、その子の選択です。
大人ができるのは、その選択を焦らず・比べず・信じて見守ることかなと思います。
「友だちがいないのはダメ」「作らせなきゃ」ではなく、「その子なりのペースと心地よさを大切にしたい」というまなざしが、
こどもの“人との関わり方”に安心をもたらすのではないかと思います。